

窓際の席に、午後の日差しがやわらかく差し込んでいた。
湯気の立つカップの向こうに、彼がいる。
いつも通りの姿なのに、どこか前より近い。
テーブルの上には、二人で使い始めたノート。
今日のページには、私が書いた「嬉しかったこと」と、
彼が書いた「ありがとう」が並んでいた。
「なんかさ。」
彼が、少し照れたように笑った。
「前より、芽衣って……ちゃんと自分がある感じする。」
胸の奥が、ゆっくり温まる。
褒められたというより、見てもらえた 感覚だった。
「そうかな。」
声は自然に柔らかくなった。
「うん。前はさ、俺に合わせてくれてた。
それは優しさなんだけど……どこか苦しそうだった。」
私はペンを指で転がすように触れる。
ノートの余白が、静かに次の物語を待っていた。
「でも今は違うよ。」
彼は、まっすぐな目で言った。
「自分で考えて、自分で選んでる感じがする。
なんか……頼もしい。」
その言葉に、呼吸が深くなった。
「じゃあさ。」
彼はノートの端をそっと撫でる。
「その“前の芽衣”にも、教えてあげられたらよかったね。」
胸の奥が、すこし震えた。
でも、痛みじゃない。確かな歩みの跡だった。
「……うん。手紙、書いてみようかな。」
「いいと思う。」
彼は迷わず微笑んだ。
「その気持ち、ちゃんと届くよ。」
カップの湯気が、ゆっくり空へ溶けていった。
最初の一歩は、本当に小さなものだった。
あの日までの私は、彼からの誘いが来るかもしれないと思うと、予定を空けてしまっていた。
「いつでも会えるようにしておくこと」が、好きの証だと信じていた。
でも実際は、
自分の時間を彼に明け渡して、息を止めているような恋だった。
鑑定のとき、占い師の声は静かだった。
「あなたは、“待つ恋”を続けてきたんですね。
でも、その優しさは、“あなたの時間”を犠牲にした上に成り立っていたのかもしれません。」
言われた瞬間、胸の奥が、小さく痛んだ。
たしかに、そうだった。
その帰り道、手帳を開いた。
ずっと「空白」で残していた週末に、そっとネイルサロンの予約を書き込んだ。
予定を書いた瞬間、
ページが“私のもの”になった気がした。
「彼に会う可能性」のために空けていた場所に、
“私が過ごしたい時間”を置いた。
ただそれだけのことなのに、
世界がほんの少し、私のほうへ傾いた気がした。
忘れたくないから、そっと手帳を閉じた。
その小さな音は、私の中で確かに響いた。
彼がお弁当を食べたときの笑顔は、まだ胸の中にあった。
あの瞬間、私は「彼からの反応」よりも、
「渡せた自分」が嬉しかった。
でも、それでもまだ、ひとつだけ怖さが残っていた。
——私の気持ちは、ちゃんと届いているのだろうか。
会っている時間は心地いい。
でも、言葉にしないまま溶けていくものが、
胸のどこかに積もっていた。
その夜、鑑定の電話をつないだ。
「彼は、あなたの“想い”を受け取っていますよ。
ただ、言葉にしてもらえると、もっと安心できる人ですね。
あなたの心を、あなたの言葉で渡してあげてください。」
その言葉は、やさしく背中に触れた。
気持ちを話すのは、まだ少し怖かった。
声にすると、心がむき出しになる気がしたから。
だから私は、ゆっくり丁寧に、手紙を書くことにした。
思いつくたびに消して、また書き直した。
夜が静かに深まっていくのといっしょに、
胸の形もすこしずつ整っていった。
渡した日、彼はすぐには開かなかった。
封筒をそっと手で包んで、静かに言った。
「ありがとう。大事に読むね。」
数日後、夜道を並んで歩いていたとき、彼が口を開いた。
「気持ちを伝えるって、難しいけど…嬉しいな。」
その言葉は、まるで私の胸の声と重なっていた。
少し歩いて、同じタイミングで息を吸った。
「こういう気持ちとかさ。
見える場所に、置いておけたらいいね。」
「あ……うん。」
一拍。
「——共同ノート。」
言葉が同時に重なった。
その瞬間、
恋は “二人で育てる場所” になった。
あの日の私へ。
画面の明かりだけが灯る部屋で、
返事を待ちながら、何度も更新ボタンを押していた私へ。
「気にしないようにしよう」と言いながら、
心のどこかで、そっと祈っていた私へ。
ちゃんと、聞こえているよ。
胸の奥がきゅっとなる感じも、
言葉にできないままに落ちてしまう涙も、
自分でも理由の分からない焦りも。
それは全部、
大切に思っていたから 生まれたものだったんだ。
弱かったんじゃない。
愛がまっすぐだっただけ。
「失いたくない」と思った気持ちは、
たしかに、真剣な恋の形だった。
あの頃、私は
自分を置き去りにしていたことに気づけなかったけれど、
それでもちゃんと、
前に進もうとしていた。
ネイルサロンの予約を入れた日。
「この日なら空いてるよ」と言えた日。
震える手でお弁当を作った日。
ためらいながら手紙を書いた夜。
どの瞬間も、
大丈夫じゃなかったけど、
ちゃんと、生きていた。
あのときの私は、
何も持っていないように思えていたけれど、
本当はもう、
ゆっくりと「自分」を取り戻していたんだ。
たしかに時間はかかったし、
迷いも涙も、不安もあった。
でもね。
その全部が、
今の私を作っている。
だから、もう責めなくていいよ。
「どうしてあんなに不安だったんだろう」なんて、
振り返って笑わなくていい。
ただ、
「生きていたな」と思ってあげてほしい。
それだけで、十分だよ。
あの日の私へ。
あなたはちゃんと、ここまで来たよ。
ゆっくりでよかった。
迷ったままでよかった。
その歩き方のまま、
これからも進んでいい。
ノートを閉じると、カフェの窓の向こうで夕暮れがゆっくり滲んでいた。
その色は、特別じゃないのに、不思議とあたたかかった。
「これから、どうなるんだろうね。」
私が言うと、彼は少し考えてから、やわらかく笑った。
「さあね。
でも……一緒に考えていけるなら、それでいいかな。」
その言い方が、未来を約束する言葉よりずっと安心した。
手をつなぐでもなく、寄りかかるでもなく、
ただ、同じ方向に身体が向いている。
きっと、恋は“決める”ものじゃなくて、
こうして“続ける”ものなんだ。
「帰ろっか。」
並んで立ち上がる。
歩幅は、もう同じだった。










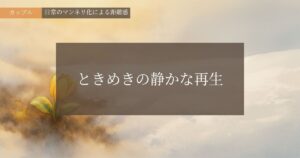

コメント