

日曜の夜、
ベッドにうつ伏せのまま、天井を見ていた。
“将来の夢”って、なんだろう。
彼と暮らす未来は、ぼんやり思い描ける。
隣で笑っている姿も浮かぶ。
でもその先を見ようとすると、
胸の奥にふわりと空白が広がってしまう。
「……私、何ができるんだろう。」
静かにこぼれた言葉は、
悲しみではなく、“まだ形のないもの”を見つめる感触だった。
ふと、両親のことを思い出した。
父と母は、いつも完全に分かり合っているわけじゃない。
小さなすれ違いは日常にある。
でも、夕飯の食卓には必ず二人分の箸が置かれていた。
「続ける」ことが、二人にとっての愛の形だった。
この前まいちゃんとランチに行ったとき、
まいちゃんは笑いながら言っていた。
「うちはさ、言い合いも多いよ。でも、結局一緒にいる。
なんか…積み重ねってそういうことじゃない?」
その言葉が、胸の中に今も残っている。
買い物帰りにすれ違った老夫婦。
歩幅は揃っていなかった。
けれど、片方が少し立ち止まると、
もう片方も自然と足を止めていた。
完璧ではない。
でも、寄り添い方を育ててきた人たちの歩き方だった。
未来は、最初から“描けるもの”じゃない。
描けないことは、
何かが足りないっていう証明じゃない。
ただ、
“まだ育っている途中”なだけ。
そう思ったら、
胸の奥に、かすかに灯りがともった。
不安と、
ほんの少しのワクワクが、
同じ場所に並んで座っているような感覚。
そのとき、机の上のノートが目に入った。
先日書いた「今の私のしたいこと」のページ。
あのときの言葉は、
すぐ近くの私とつながっていた。
今は、もう少し先。
「これから」の私に触れてみたいだけ。
欠けているんじゃない。
育ちきっていないだけ。
その気づきが、
静かに私を支えてくれた。
ノートを開いたまま、
しばらくペンを持って止まっていた。
“未来”ってどう言葉にすればいいんだろう。
書けない。
いや、書く言葉がないんじゃなくて、
胸の奥にあるものが、まだ形になっていない。
その感覚を確かめるように、
ゆっくり呼吸をした。
「…この気持ちに名前をつけたい。」
誰かに答えを決めてもらいたいんじゃない。
ただ、
いまの私はどこに立っているのかを知りたい。
そのとき、思った。
「そうだ、話してみよう。」
電話占いに“頼る”んじゃなくて、
自分の言葉を見つけるために話してみる。
そう思えたのは、
きっと私が少しずつ進んできたからだ。
通話ボタンを押す指は、前より落ち着いていた。
私はいつものように通話ボタンを押した。
呼び出し音が一回鳴るか鳴らないかのうちに
占い師さんの声が降りてきた。

芽衣さん、こんばんは。
今日も来てくれてありがとう。
その“ありがとう”が、
いつだって心の準備をしてくれる。
……今日は、未来のことを話したくて。
私は、天井を見つめていたときの気持ちを
そのまま言葉にした。
結婚の先のイメージがうまく描けないこと。
自分には何もないんじゃないかと感じたこと。
でも、そう思う自分を責めたいわけじゃないこと。
占い師さんは、途中で遮らなかった。
その沈黙は、ただ寄り添うためのものだった。



芽衣さん。
未来ってね、最初から“形”があるものではないんですよ。
落ち着いた声で、そっと言葉が置かれる。



二人で少しずつ育てて、
“未来だったもの”があとから形になるんです。
心の奥が、ゆっくり息を吸い込む。



芽衣さんは、未来をちゃんと考えられる人です。
それはとても美しいことなんです。
言い切るその声に、嘘がなかった。



でもね、芽衣さん。
ここで大切なのは 誰かの未来に合わせること ではなく、
“芽衣さんが、どんな自分でそこに立ちたいか” なんです。
私は、静かに目を閉じた。
彼を幸せにするために、ではなく?
気づいたままの言葉が出た。



そうです。
“芽衣さんが、幸せを感じられる自分であること。”
その自分で彼の隣に立てたとき、
自然と大切にし合える関係は育っていきます。
それは、
「足りない私を埋める」未来ではなく、
「育っている途中の私と、誰かと共に歩く」未来だ。
じゃあ……私は、何をしたらいいですか?
問いは、頼るためのものではなかった。
ただ、未来へ踏み出すための確認だった。



小さなことでいいんです。
芽衣さんが“こうありたい”と思う自分に、
ほんの一歩近づける行動。
少しだけ、心が暖かくなる。



その積み重ねは、やがて自信になっていきます。
そしてその自信は、きっと誰かを優しく照らします。
“誰かのため”ではなく、
“理想の自分に近づくために、誰かへ向けて手を伸ばす”。
その順番が、未来を静かに育てていく。
通話が終わったあと、
私はゆっくり深い呼吸をした。
泣きたいわけじゃない。
苦しいわけでもない。
ただ──
「進んでみたい」と思った。
その感覚は、確かに私のものだった。
深夜のキッチンは、
昼間よりも落ち着いた表情をしていた。
外から聞こえる音はほとんどなくて、
冷蔵庫の稼働音だけが、規則的なリズムを刻んでいる。
「…よし。」
私はエプロンをゆっくり結んだ。
鏡に映る自分は、少しだけ緊張していて、
でもその緊張はどこかあたたかかった。
目的はひとつ。
“理想の私”に、少しだけ近づいてみること。
彼のために完璧な料理を作りたいんじゃない。
誰かの基準に合わせた「ちゃんとした私」になりたいわけでもない。
ただ──
未来に向かって、ひとつ手を伸ばしてみたかった。
レシピ本を開く。
ページの端はまだ硬くて、
新品の紙の匂いがした。
「まずは…卵焼き。」
卵を割る音が、
やさしく夜に溶けていく。
手つきはぎこちない。
火加減も上手くつかめない。
巻こうとすると、形は少し崩れる。
「……ちょっと、いびつ。」
でも、不思議と嫌じゃなかった。
むしろ、
「できない自分も、ちゃんと私なんだ」
と思えた。
その気づきが、
胸の奥にそっと灯りをともす。
次に、野菜を洗って、切る。
トントン、という包丁の音が静かな部屋に跳ねる。
時間はかかる。
手際はよくない。
でも──
ゆっくりでいいということを、私は知り始めていた。
最後に詰めたお弁当は、
雑誌に載っているような完成度からは程遠かった。
だけど、
そこには、
今日までの私と、
今日始まった私が並んでいた。
「……よし。」
小さく息を吐く。
その夜、布団に入ったとき、
胸の奥がほんのりあたたかかった。
誰かを思う気持ちから生まれた行動が、
同時に“私を育てている”ことに気づいたから。
翌日のデートで、
私がそっと差し出したお弁当を見て、彼は目を丸くした。
「え、これ…芽衣が?」
「うん。まだ全然上手じゃないけど。」
「いや、すごいよ。嬉しい。」
その声は、驚きでも感動でもなくて、
“受け取るための声”だった。
食べながら、彼は何度も「うまいな」と言った。
その言い方は特別じゃなくて、
なんでもない時間の中にそっと置かれるような、やさしい温度だった。
帰り道、駅までの歩道を並んで歩いた。
前は、どちらかが少し先を歩いていた気がする。
知らないうちに、ついていこうとしていたり、
追いかけられている気がしたこともあった。
でも今日は、
私の歩幅と、彼の歩幅が、自然と同じ速さになっていた。
どちらかが合わせた感じは、なかった。
ただ、同じ方向に進んでいた。
街灯に照らされた影が、
アスファルトの上で長く伸びる。
重なり合うでもなく、
離れるでもなく、
そっと並んでいた。
それを見た瞬間、
胸の奥に、あたたかいものが広がった。
未来は、まだはっきりしていない。
輪郭は薄いし、色もついていない。
でも──
“歩ける道” としてそこにある気がした。
「今日、ありがとう。」
彼がぽつりと言った。
私は小さく、うなずいた。
言葉は少なかったけれど、
それで十分だった。
私はまだ途中。
でも、途中のままで、ちゃんと進んでいる。
その夜、
ノートの隅に一文だけ書いた。
【並んで歩けた日】
ページを閉じると、
灯りが静かに胸の奥でともっていた。
消えないままで。












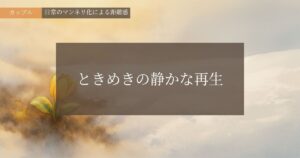


コメント