「芽衣、今日昼どうする?」
声をかけられて、顔を上げる。
まいちゃんが、コートを腕に引っかけながら私を見ていた。
「カフェ行かない?」
私はいつもの調子で笑って返す。
笑うことは、まだできる。
「いいね。あそこ、日当たりいいし。」
二人で外に出ると、冬の空気は冷たかったけれど、日差しはやわらかかった。
カフェは昼時で少し混んでいた。
けれど、ちょうど窓際が空いていて、ふたり並んで腰を下ろす。
テーブルに落ちる光が白くて、
その明るさが、心のどこかに触れた。
メニューを開いて、特に迷わず同じものを頼む。
私もまいちゃんも、そういうところは似ている。
「最近さ。」
まいちゃんが、紙ナプキンの端を折りながら言う。
その声には、少しだけ確かめるような色があった。
「彼と、会ってるんでしょ?」
カップを持つ手が、ほんの少しだけ止まった。
でも、それに気づかれたくなくて、すぐ持ち直す。
「うん……まあ、会ってるよ。
なんか、ちゃんとは言えないんだけどね。」
笑顔に“ごまかし”を混ぜてしまうのは、習慣みたいなものだ。
「そっか。」
まいちゃんは、それ以上追わなかった。
ただ“わかったよ”のかわりに、
静かにコーヒーを口に運んだ。
ちくり、と胸の奥が痛む。
追及されない優しさのほうが、刺さることもある。
「ねえ、昨日のドラマ見た?」
まいちゃんが話題を切り替えてくれた。
なにも触れすぎない、でも放っておくわけでもない距離感。
「あれね!あの展開は反則だよね。」
私は、ちゃんと笑った。
笑えたことに、少しほっとした。
だけど、
その笑いはどこかで薄かった。
帰り道、駅の階段を降りながら、
私はスマホを何度も見てしまう。
通知は来ていない。
けれど、画面を見る手は止まらない。
「いつか来るはず」
「来るかもしれない」
その“かもしれない”が、
思っている以上に私を支えていた。
揺れていることに、まだ私は気づいていなかった。
家に帰ると、部屋の空気は少しひんやりしていた。
コートを椅子に置き、バッグを手放して、深呼吸をする。
何をするでもなく、
スマホを手に取ってしまう。
既読は、ついている。
でも、返事はない。
少しだけ、胸が沈んだ。
それでもまだ、完全には落ちない。
「また、誘ってくれるはず。」
そう信じる気持ちが、まだあった。
信じている、というか——
信じたい 言葉のほうが、しっくり来た。
だけど、
その信じたい気持ちが、私の生活を支配している気がした。
「……相談してみようかな。」
自分で言ったその言葉に、少し驚いた。
占いを受けることに対して、
偏見はなかったけれど、縋るように頼るのは違うと思っていた。
でも、
「今のままだと苦しくなる」
その予感だけは、はっきりしていた。
予約ページを開いた指先が、少し震える。
うまく話せるかな。
理解してもらえるかな。
変に思われないかな。
不安は尽きないのに——
それでも、通話ボタンを押した。
心臓が、胸の近くまでせり上がるような感覚。

今日はどうされましたか。
優しい声が耳に触れた。
あたたかい。
でも、すぐに涙が出るほど安心ではない。
触れるのに、壊れやすいような声。
……好きな人がいて。
付き合ってるんです。
でも、私ばかり、予定を空けちゃってて。
言葉にした瞬間、
はじめて、胸の奥に自分の本音が落ちた。



待ってしまうんですね。
その声は、責めなかった。



待つのは、悪いことではありません。
ゆっくり、呼吸を合わせるように言葉が続いた。



ただ、芽衣さんは
“会える可能性” を信じるために、
自分の時間をまるごと差し出してしまっている。
少し、息が止まる。



それはね、やさしいからなんです。
やさしい人は、自分の時間を削ってでも、相手を受け止めようとするから。
胸の奥に、あたたかさと痛みが同時に生まれた。



でもね。
そのやさしさは、あなたを細くしてしまうこともあるんです。
返事はできなかった。
でも、確かに聞こえた。
心に、静かに沈んでいく声だった。
部屋の明かりを少し落とすと、
空気がゆっくり沈んでいくのが分かった。
深呼吸をすると、胸の奥にまださっきの声の余韻が残っている。
“差し出してしまっている。”
その言葉は、すぐに理解できるものではなかった。
だけど、確かに心のどこかに触れていた。
私は机の引き出しから、手帳を取り出す。
表紙は少し角が丸くなっていて、
ずっと使っていたはずなのに、
中身は驚くほど「空白」だった。
日曜、月曜、土曜。
休みの日の欄だけ、まるで呼吸を止めたみたいに真っ白。
ページを指でなぞる。
紙のざらりとした感触が指先に残る。
「……どうして、空けてたんだっけ。」
問いかける声は、自分に向けたものだった。
思い出そうとしたとき、
胸の奥の柔らかい場所が、そっと疼いた。
あの日。
夕方のスーパーで買い物中に、突然スマホが震えた。
『今日会えない?』
その文字を見た瞬間、
胸の奥に光が射し込んだみたいに、
世界が少し明るく見えた。
買い物かごを押す手が軽くなって、
今日作ろうと思っていた夕飯のことなんて、
全部どうでもよくなってしまった。
家までの帰り道に見えた街灯の光は、
いつもより少しあたたかく見えた。
駅前で彼の姿を見つけたとき、
心が一瞬だけ「跳ねる」感じがした。
あの感覚。
あれが、まだ私の中に生きている。
あの嬉しさを、私は忘れられていなかった。
手帳に視線を戻す。
「誘われるかもしれない日」を空けていたのは、
その“嬉しさ”を、また感じたいからだった。
苦しかった日よりも、
嬉しかった日のほうが、
ずっと強く心に残ってしまう。
だから——
「期待してしまう私」は、
ただの弱さじゃない。
“好きでいたい心”の、正直な形。
だけど同時に、
その期待に自分の全部を預けてしまうと、
私の生活は、私のものじゃなくなる。
この二つの気持ちは、
どちらも本物だった。
私は、
どちらか一方を選べるほど強くはなかった。
ゆっくり、息を吸う。
胸の奥が少しだけ痛む。
「……それでも。」
声に出したほうが、
思考よりも本音に近づける気がした。
「このままだと、私は苦しくなる。」
占い師さんは、何も押しつけなかった。
正解も提示しなかった。
ただ、
“私が自分で気づける余白” を残してくれた。
だから今のこの言葉は、
誰かに言わされたものじゃない。
私の中から生まれたものだった。
「行きたいんだよね、本当は。」
ネイルサロンの看板を、
何度も通り過ぎた日のことを思い出す。
入り口のガラス越しに、
誰かが指先をきれいにしてもらっているのを見ると、
なぜか胸の奥が少しだけ温かくなるのに。
でも、私はいつも通り過ぎた。
「彼から誘われるかもしれないから。」
そのたったひとつの理由で。
だけど今は——
ほんの少しだけ、違う。
「行きたい」
その気持ちを、
やっと、私が私に向けて言えた。
指先がスマホに触れる。
ゆっくり、予約ページを開く。
心臓がまた、静かに強く打ちはじめる。
鼓動が、耳の奥に響く。
「まだ、彼を嫌いになったわけじゃない。」
「期待している私を、やめるわけじゃない。」
「ただ、私の時間を全部渡すのは、やめたい。」
まるで、
両手の中でバランスをとるように。
画面の「予約する」のボタンに触れた瞬間、
呼吸が止まった。
押すまでに、
あと一呼吸だけ必要だった。
その一呼吸は、
「覚悟」ではなく、
「自分を見捨てないための時間」 だった。
——押した。
音はしなかった。
でも、心のどこかで、なにかがゆっくり動いた。
手帳にペンを置く。
震えは、もうなかった。
日曜:ネイルサロン
その字は、
“自分を取り戻すための、最初の小さな旗” だった。
私はまだ、彼を想っている。
その気持ちは、ちゃんと生きている。
でも、
その隣に “私自身” も、
ちゃんと座らせたかった。
今日は、
そのための一日だった。
ネイルサロンの予約日。
朝、目を覚ますと、部屋の空気がいつもよりやわらかく感じた。
カーテンの隙間から差し込んだ光は淡くて、
まるで、今日だけは私を静かに起こしてくれたみたいだった。
洗面台の前で顔を洗う。
水が頬に触れたとき、
自分の体温がふっと戻ってきた感じがした。
「行っていいんだよね、私。」
声にすると、心が少しだけ追いついてくる。
サロンの扉を押した瞬間、
小さなベルが柔らかく鳴った。
店内には淡いピンクと木目の匂い。
静かに流れるBGMのピアノが、
胸の奥の固まりをゆっくりほぐしていく。
「いらっしゃいませ。ご予約いただいてましたね。」
ネイリストさんの声は、
占い師さんの声と同じくらい、やさしかった。
席に座ると、
指先がテーブルにそっと置かれる。
いつもは気にもしなかった自分の手が、
今日はなぜか、すごく愛おしく見えた。
「どんな色にしますか?」
「この色……かわいいなって思ってて。」
サンプルの中から選んだ、
淡い桜色。
派手すぎない。
でも確かに、あたたかい色。
爪に色がのっていく。
ブラシの先が指先をなぞるたび、
心がゆっくりほどけていく気がした。
私は今、
誰かの都合のためでも、
“誘われる可能性” のためでもなく、
自分のためにここにいる。
それが、ただそれだけが、
胸の奥の深いところに静かに灯をともした。
帰り道、
街の風は少し冷たかったけれど、
指先の色があたたかかった。
スマホを開く。
通知は、来ていない。
でも——
胸が沈まなかった。
「そっか。」
まいちゃんの声と同じ響きで、
私はそっと呟いた。
それは諦めじゃなくて、
私が、私を見捨てなかった証 だった。
部屋に戻り、手帳を開く。
日曜:ネイルサロン
その文字は、もう“余白を埋めた文字”じゃない。
“私として生きる時間を取り戻した証” になっていた。
ページを閉じるとき、
胸の奥で小さく息が弾んだ。
「大丈夫。」
心が、そう言った気がした。
恋はまだ終わっていない。
期待も、希望も、まだそこにある。
ただ、
その隣に、私自身も立っている。
今日は、その始まりの日だった。













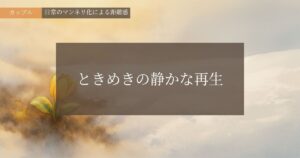


コメント