

仕事を終えた帰り道、夜の空気は少し冷たかった。
駅前のロータリーでは、タクシーが何台か並んでいて、
そのヘッドライトの光が、ぼんやり滲んで見える。
電車に揺られながら、
いつのまにかスマホの写真フォルダを開いていた。
昨日、彼と過ごしたときに撮った写真はない。
けれど、あの瞬間の表情は、はっきり思い出せる。
「……あ、笑ってたな。」
声にすると、胸の奥があたたかくなった。
目を閉じれば、すぐに蘇る。
お弁当箱を開けた彼が、少し驚いたように目を丸くして、
それから、ゆっくり、やわらかく笑ったあの表情。
「これ、芽衣が作ったんだよね。
すごいな。…おいしい。」
あのとき、私の胸はふわっと広がった。
湯気のように、じんわり広がって、
気づけば呼吸が深くなって。
「嬉しかったな……。」
小さく呟いた声は、電車の走行音に消えていった。
玄関の鍵が「カチャ」と鳴る音。
部屋に入ると、ほんのり生活の温度が戻ってくる。
いつものようにコートを脱いで、
バッグを置いて、髪をほどく。
部屋着に着替え、洗面台で手を洗うと、
指先に残った外の冷気がすっと溶けていく。
ケトルに水を入れて、スイッチを押す。
「コト…コト…」という小さな音が部屋に広がる。
照明は天井の明かりをつけず、
リビングのスタンドライトだけにした。
やわらかい光の中だと、
心がすぐに本当の形を見せるから。
シンクの横に、お弁当箱が置いてあった。
昨日、丁寧に洗って乾かしたもの。
触れるつもりはなかったのに、手が伸びてしまう。
つるんとした表面に、そっと指先が触れた。
その瞬間、
胸の奥がふわりと揺れた。
「……嬉しいって、こういう感じなんだ。」
言葉にしたわけではなく、
ただ、気持ちが自然に浮かんできた。
でも、そのすぐあとに
心が少しだけ、きゅっと縮こまった。
嬉しいのに、
どうして、胸の奥が不安で震えるんだろう。
嬉しいはずなのに、
なぜか「もし」を考えてしまう。
「もし、またうまくいかなくなったら。」
「もし、期待しすぎてしまったら。」
嬉しさの影に、
小さな不安が静かに座っている。
それは、昨日の幸せを否定するものではなくて、
むしろ、それが本当に大事だった証のように思えた。
「……そうだよね。大切にしたいって気持ち、なんだよね。」
湯がわいた音がして、
ケトルが小さく息を吐いたように止まる。
カップにお湯を注ぐと、
ふわっと白い湯気が立ちのぼった。
それは、まるで胸の中の気持ちの形が可視化されたように見えた。
ソファに腰を下ろし、
あたたかいカップを両手で包む。
「私、なんであんなに嬉しかったんだろう。」
問いを投げかけると、
答えは、静かに、でもはっきり返ってきた。
私は、この人と一緒に育ちたいからだ。
彼に「してもらう」関係じゃなくて、
私も「渡せるもの」を持っていたい。
昨日のお弁当は、たとえばその小さな一歩だった。
「でも、まだうまくできないな。」
そう思った瞬間、胸がきゅっとした。
不安は、まだそこにいる。
だけど、前みたいに居座っているわけじゃない。
不安は、
この気持ちが本物だから生まれている。
嬉しさと、不安。
どちらも、ちゃんと私のもの。
強くならなくていい。
確信がなくてもいい。
迷ったままで、かまわない。
私は、
ただ、この気持ちを失いたくないだけ。
「大切にしたいな。」
そう呟いた声は、
部屋のやさしい灯りに溶けていった。
部屋の灯りは、スタンドライトひとつだけ。
天井の明かりをつけない夜は、心の輪郭がそのまま浮かび上がる。
机の上にノートを置いて、ゆっくり開いた。
白いページを前にすると、まるで「さあ、どうする?」と問われているようで、
胸の奥が少しだけそわそわする。
昨日のことを書こうと思っているのに、
ペン先は紙の上に触れたまま動かなかった。
「嬉しかったよ」と言われたこと。
その声のあたたかさ。
こっちを見て笑ってくれた横顔。
その全部が、まだはっきり残っている。
それをそのまま文字にすればいいだけなのに、
なぜかできない。
「……怖い、のかな。」
声に出してみると、胸の奥が一度だけ波打った。
気づかないふりをしていた気持ちに、そっと触れた音。
嬉しいと、怖いは、いつも一緒に来る。
大切になればなるほど、失うことが頭に浮かぶ。
それを知っているからこそ、慎重になる。
でも、たしかにある。
あの日から胸に灯った、小さな光。
「…言葉に、してみたいんだ。」
ちゃんとしたいとか、うまく伝えたいとかじゃなくて、
ただ、いま思っていることを、そのまま。
そんな気持ちを抱えたまま、通話ボタンを押した。
呼び出し音がゆっくり、一定のリズムで続く。
息をひとつだけ深く吸って、吐いた。
「芽衣さん、こんばんは。」
その声を聞いた瞬間、ふっと肩の力が抜けた。
まるで、座る場所を差し出されたみたいだった。
「こんばんは。
…ちょっと、話したいことがあって。」
「ええ。慌てなくて大丈夫です。
ゆっくり、言葉にしてみましょう。」
少し間を置いてから、昨日のことを話した。
お弁当を喜んでくれたこと。
あの笑顔を見て、胸が温かくなったこと。
それと同じくらい、怖さもあったこと。
「嬉しいのに、不安にもなったんです。」
「不安は、“大切にしたい気持ち” の影ですよ。」
影、か。
たしかに、そう言われると、どこか腑に落ちた。
「芽衣さんは、彼から何かをしてもらう恋ではなくて、
一緒に育ちたい恋を選んだんです。」
胸の奥が、ゆっくりとほどけていく。
「……育ちたい、です。
でも、まだ上手に言えなくて。」
「上手じゃなくていいんです。
育つ恋は、いつだって不器用です。」
言葉の温度が、湯気のように静かに触れた。
「じゃあ……手紙に、してみようと思ってます。」
「それは、とても良い選択です。
言葉を急がない恋は、長く続きますよ。」
通話が終わっても、部屋は静かなままだった。
ノートは開いたまま。
さっきより、ページが近く感じる。
ペンを持って、ゆっくりひとつだけ書いた。
「嬉しいって、ちゃんと大事にしていいんだ。」
それだけで、十分だった。
今日は、これで終わりにした。
すぐに手紙を書かなくていい。
この感情がちゃんと落ち着いて、形を持つまで、
そばに置いておきたい夜もある。
カップの中のお湯は、少しぬるくなっていた。
そのぬるさが、やさしかった。
「大切に、したいな。」
小さくこぼした声は、
静かな部屋の中で、そっと灯りのようにとどまった。
カフェの窓から見える夕暮れは、
冬の空気を含んで、少しだけ透明だった。
「お疲れ。」
彼はいつもと同じ調子で微笑んだ。
その“いつも通り”に、救われることがある。
言葉がいきなり喉に引っかかりそうだったので、
コーヒーを一口飲む。
湯気の向こうに、私の気持ちが静かに揺れていた。
「これ……渡したいものがあって。」
封筒をテーブルに置いた瞬間、
自分の心臓の音が、ひとつだけ強く響いた気がした。
「読んでいい?」
「うん。でも……あとで、ゆっくりの方が嬉しい。」
彼は、すぐに封を開けずに、
両手でそっと包み込むように持った。
その仕草が、それだけで、
私の気持ちを「大切に扱う」という行為になっていた。
言葉にしないものが、確かにそこにあった。
その日は、それ以上話さなかった。
無理に“何か”を確かめる必要はない気がした。
別れ際、彼が小さく言った。
「ありがとう。受け取ったよ。」
ただそれだけが、まっすぐで、やさしかった。
仕事帰り、空気は冷たかった。
街灯の光が、歩道に小さな影をいくつも落としていた。
「少し歩かない?」
彼からのメッセージはそれだけだった。
会ってすぐ、手紙の話は出ない。
ただ、ゆっくり歩く足音が並んで響く。
しばらくして、彼が口を開いた。
「……読んだよ。昨日の夜。」
風が頬を撫でる音が、間を静かに埋めた。
「上手に言えないけどさ。
あれ、すごく…あたたかかった。」
言葉を探している声だった。
それは、すぐに形にならなくていい種類の気持ち。
「ありがとう。読んでくれて。」
そう言ったとき、胸の奥でそっと何かがほどけた。
「気持ちを伝えるってさ、難しいな。」
彼が視線を前に向けたまま呟く。
「でも……嬉しいな。」
「うん。難しい。でも……嬉しい。」
また同じ言葉が、同じ間で重なる。
その偶然が、奇跡なんかじゃなくて、
ゆっくり育ててきたものなんだと思えた。
公園の前で足を止める。
街灯がふたりの影をゆっくりと重ねた。
「ねえ。」
「うん?」
声がまた重なって、二人で小さく笑った。
「こういう気持ちとかさ。」
「考えてることとか。」
「置いておける場所があったら、いいよね。」
少しだけ沈黙。
でも、その沈黙は冷たいものじゃない。
一拍。呼吸がそろう。
「「共同ノート。」」
言葉が重なった瞬間、
胸の奥に、あたたかい灯りがともった。
名前は、誰かに教わったわけじゃない。
ふたりで、同じ場所にたどり着いた名前だった。
「……なんか、いいね。」
「うん。すごく、いい。」
笑いあう声は、夜の空気に静かに溶けていった。
灯りは、ちゃんと前を照らしていた。
ページをめくる未来は、
まだ形ははっきりしていない。
でも、一緒に探していける気がする。
「これから、ゆっくりだね。」
「うん。ゆっくりでいい。」
歩幅は、もう同じ速度だった。










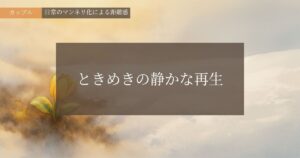


コメント